【税理士監修】個人事業主が活用できる福利厚生の例は?どんなケースなら経費計上可能?
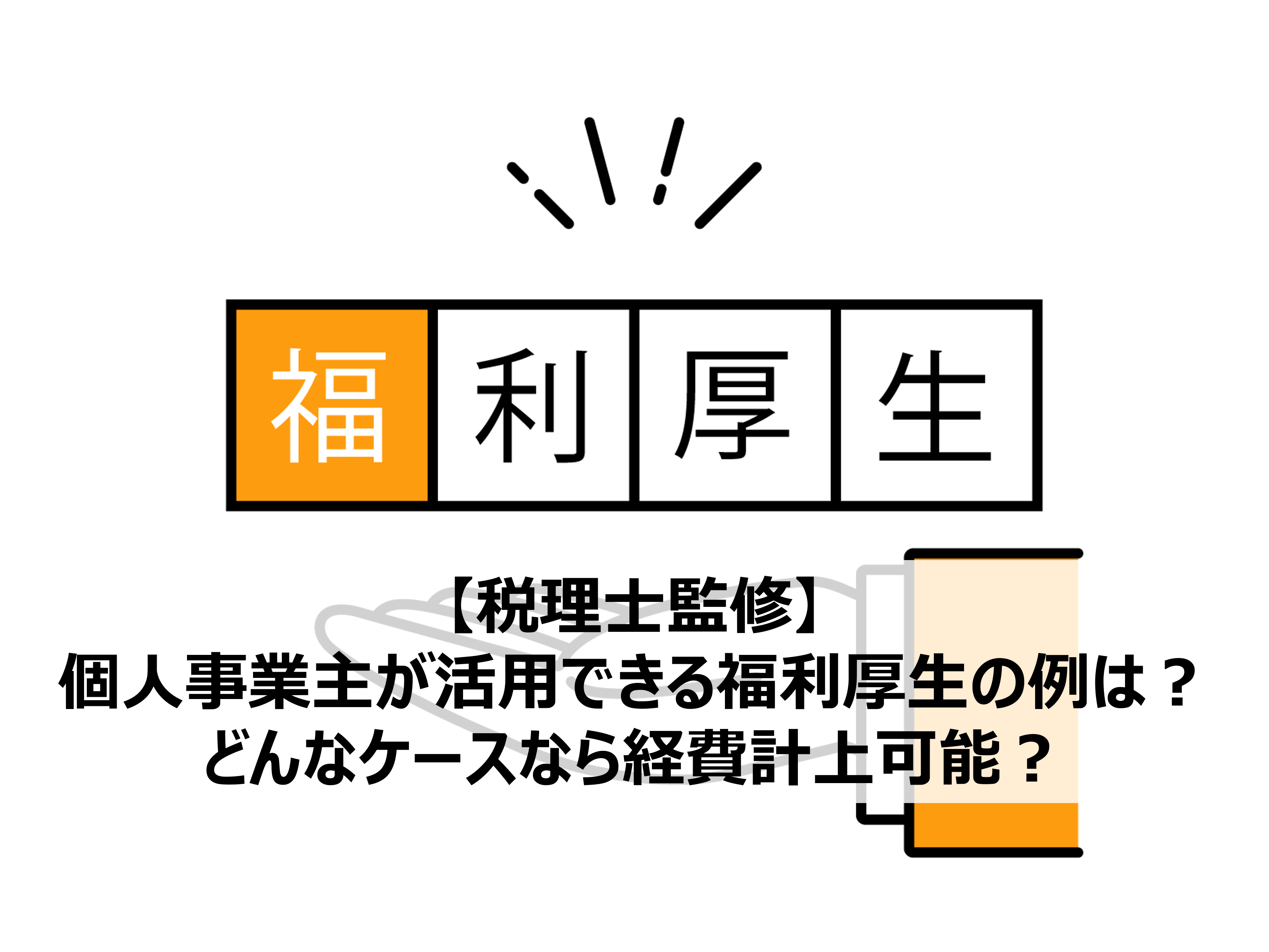
※こちらの記事は長谷工コミュニティが運営するビステーションのプロモーションを含みます。
個人事業主も、従業員を雇用している場合、導入した福利厚生にかかった費用を経費計上することが可能なケースがあります。福利厚生を活用することで、事業主は節税をしつつ、従業員満足度をあげたり、採用力を強化することができます。
本記事では、税理士監修のもと、個人事業主が活用できる福利厚生の具体例や経費計上の条件、注意点などを解説します。
福利厚生とは?個人事業主も活用できる?(福利厚生費として計上できる?)
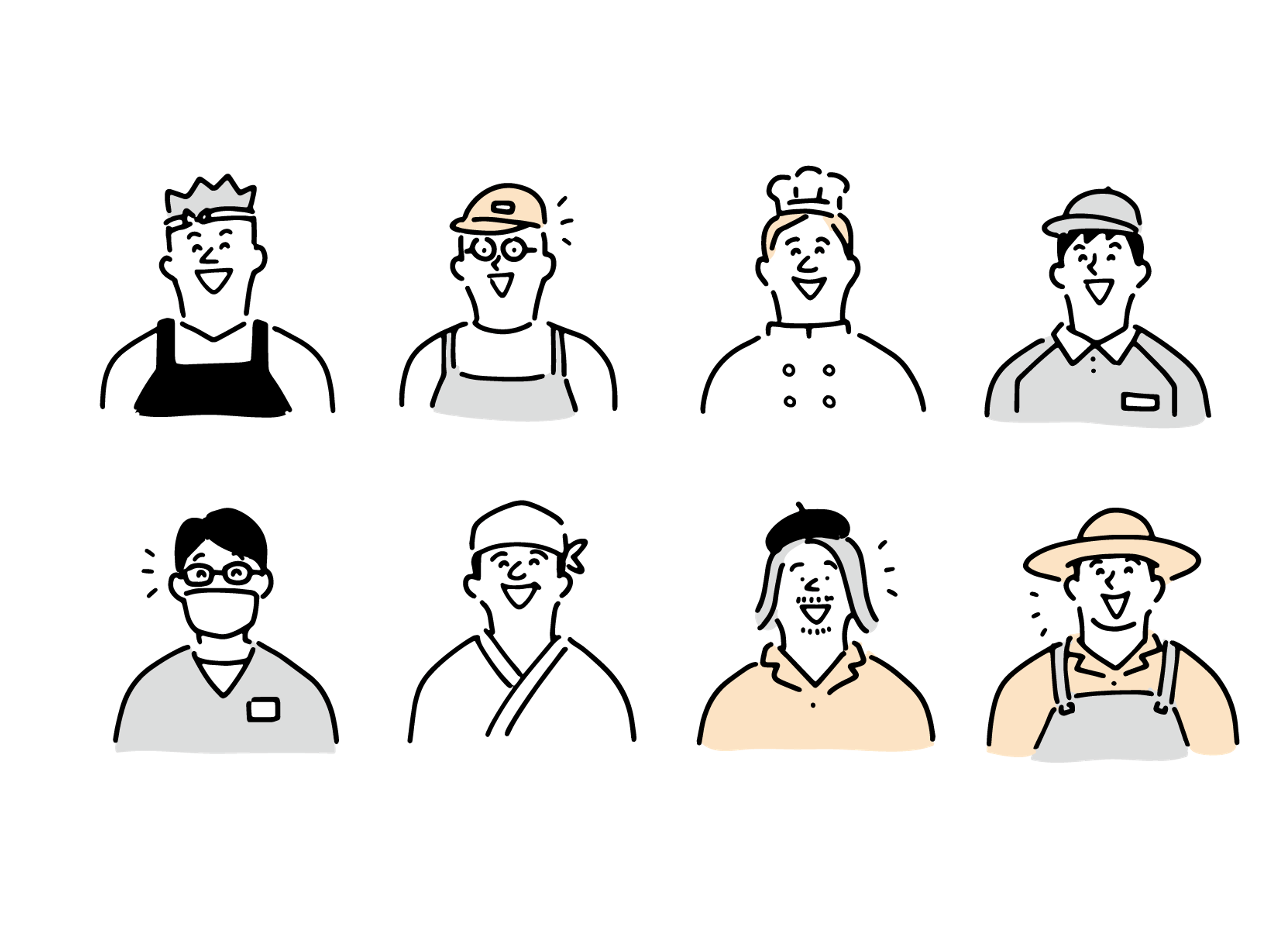
福利厚生とは?
福利厚生とは、企業や事業主が従業員に対して、給与や賞与といった基本的な労働対価とは別に提供する報酬やサービスの総称をいいます。
福利厚生が、ややわかりにくくなってしまうのは、福利厚生の中に法定内のものと法定外のものが混在することにあります。
法定福利費の具体例としては、法律で、企業の義務として定められている社会保険の企業負担分などがあります。法定外福利費としては、さまざまなものがあり、住宅手当(家賃補助)や通勤手当(交通費)、家族手当の支給、健康診断補助、社員食堂やフィットネスジムの会費負担などがあります。
福利厚生を導入することは、どのような事業者でも可能ですが、その費用を福利厚生費として経費計上するためには条件があります。
個人事業主も活用できる?(福利厚生費として経費計上できる?)
個人事業主も福利厚生を利用し、その費用を経費計上できるケースはありますが、その事業形態によって異なります。
想定できるケースとしては、大きく分けると以下の3つのケースが想定できます。
・家族以外の従業員を雇用している場合
・従業員を雇用しているが、それが家族だけの場合
・従業員を雇っていない場合
それぞれのケースについて解説します。
・家族以外の従業員を雇用している場合:〇
この場合、福利厚生を活用し、その費用を経費計上できる可能性があります。
・従業員を雇用しているが、それが家族だけの場合:✕
このケースは、基本的に福利厚生費用を経費計上できません。先述のとおり、福利厚生は「従業員のため」の支出である必要があるからです。雇用していても、それが家族だけの場合、福利厚生費用は経費計上できません。
・従業員を雇っていない場合:✕
このケースも、基本的に福利厚生費用を経費計上することはできません。
個人事業主が行う事業で、福利厚生費の経費計上が認められるための条件の大枠とは?

先ほど、個人事業主も、福利厚生を活用し経費計上ができるケースをご紹介しましたが、他にも、条件がありますので、以下にご紹介します。
それが、以下の4点の大枠です。
・家族以外の従業員を雇用していること(再掲)
・全従業員へ、平等な提供であること
・社会通念上妥当な金額や内容であること
・賃金ではなく、現金や換金性の高いものでないこと
※福利厚生の内容によって、さらに細かな条件を満たす必要があるケースもあります。
以下で、もう少し詳しく解説します。
・家族以外の従業員を雇用していること(再掲)
こちらは、再掲となりますが、個人事業主自身や家族従業員のみのための支出は原則NGとなります。
なお、ここでいう「家族」には、事業主や事業主の直系血族と事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の直系血族や、事業主や事業主の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者およびその者の直系血族なども含まれます。
参考:No.2588 学資に充てるための費用を支出したとき|国税庁
※福利厚生が、事業主の「家族」以外の従業員に対しても均等に提供されている場合は、事業主本人やその家族の分も、経費計上できる可能性があります。
・全従業員へ、平等な提供であること
福利厚生費を経費計上したい場合、特定の従業員や一部の従業員だけではなく、全従業員に対して平等に提供されるものである必要があります。
一般的に、一部の従業員だけが福利厚生を利用できる場合や、福利厚生を利用しなかった従業員に対して、その分を金銭で支給するような場合、その金額は給与と判断されます。
・社会通念上妥当な金額や内容であること
「社会通念上妥当な金額」については、どのような福利厚生を提供するか?によっても変わります。ある程度、基準が明示されているものもあれば、明確な上限金額が設けられていないものもあります。
このような場合には、会社規模や業績にふさわしい内容になっているか、同業他社と比較して高すぎないかといったことなどを総合的に勘案した金額である必要があります。
具体例として従業員向けのレクリエーション旅行の場合をご紹介します。
この場合、①旅行の期間が4泊5日以内であること。②旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。などの条件が追加で必要になります。
許容される例としては、旅行期間4泊5日で、旅行費用25万円(内使用者負担10万円)、参加割合100%の場合は、国税庁のウェブサイトで例示もされていることから福利厚生費として経費計上可能であると言えるでしょう。
一方、旅行期間が5泊6日以上のケースについては、社会通念上一般に行われる旅行ではないと例としてあげられています。
参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行┃国税庁ウェブサイト
・賃金ではなく、現金や換金性の高いものではないこと
福利厚生は、従業員の福祉の向上を目指すものです。賃金(給与や賞与)は課税の対象となります。
例えば、従業員に対して健康診断を提供したいと考えた場合、その費用を直接、事業者が医療期間へ支払えば福利厚生費として計上できますが、健康診断費用を現金で支給した場合、それは給与とみなされる可能性が高くなるため、注意が必要です。
基本的には、サービスなどである必要があります。
個人事業主が、福利厚生を導入するメリットとデメリット
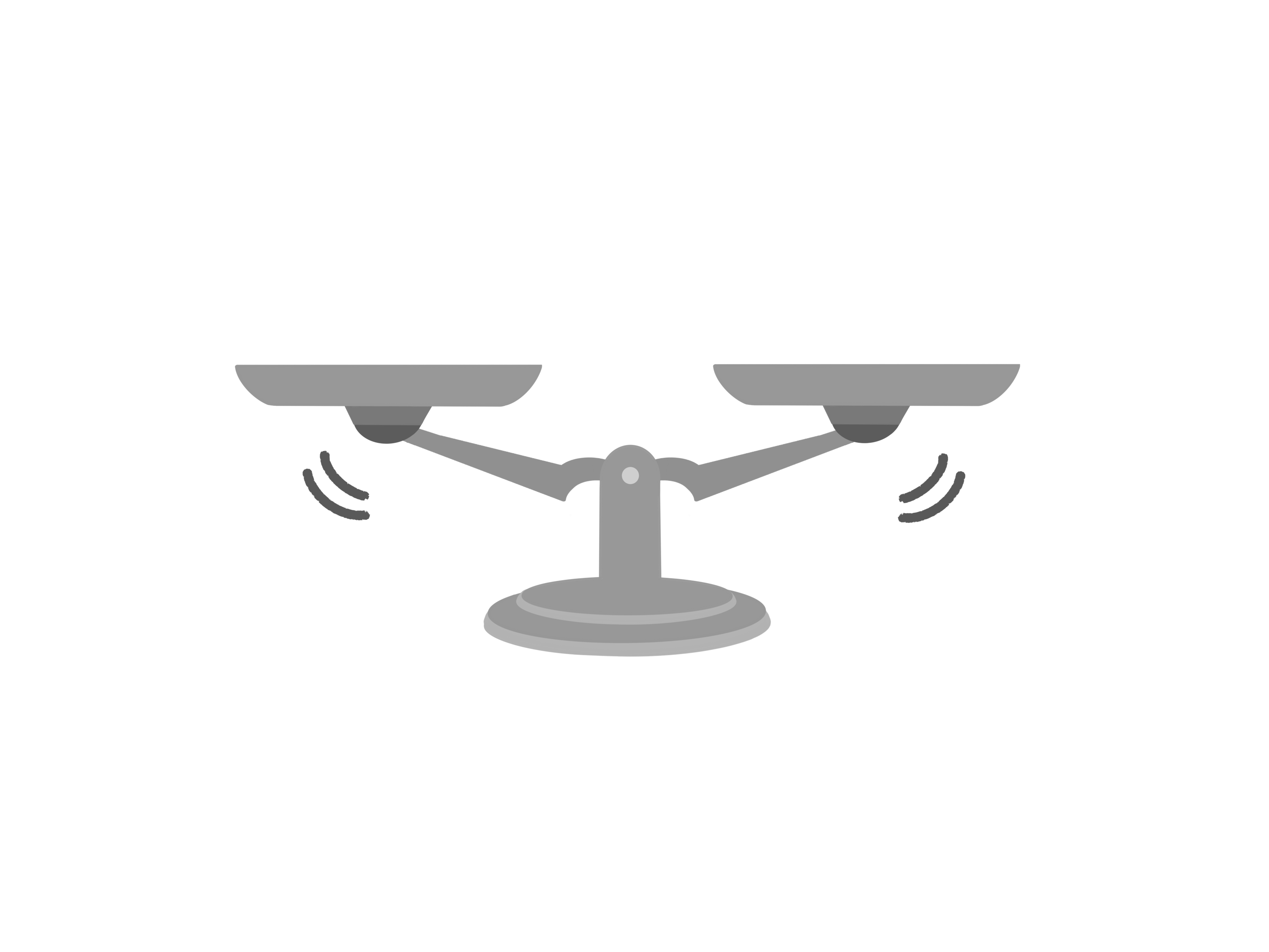
個人事業主が福利厚生を導入することで、得られるメリットとデメリットが存在します。
個人事業主が、福利厚生を導入するメリット
・人材採用力の向上効果
・従業員の満足度と定着率の向上
・生産性の向上
・事業のイメージアップ
・節税効果(条件を満たした場合に限る)
などが、あげられます。
個人事業主が、福利厚生を導入するデメリット
・費用負担の増加
・制度運用の手間や工数の増加
などがあります。
このように、福利厚生の導入には、メリット・デメリットの両面が存在しますので、導入時には慎重な判断が必要となるでしょう。
福利厚生を導入するか否かを判断する際の例としては、
・事業の安定性や利益の状況
・人材の採用や定着に関する課題の有無
・雇用している従業員の人数
・福利厚生を運用する人員の管理工数の負担
などを総合的に勘案して検討すると良いでしょう。
個人事業主が福利厚生費として利用できるものの具体的な例
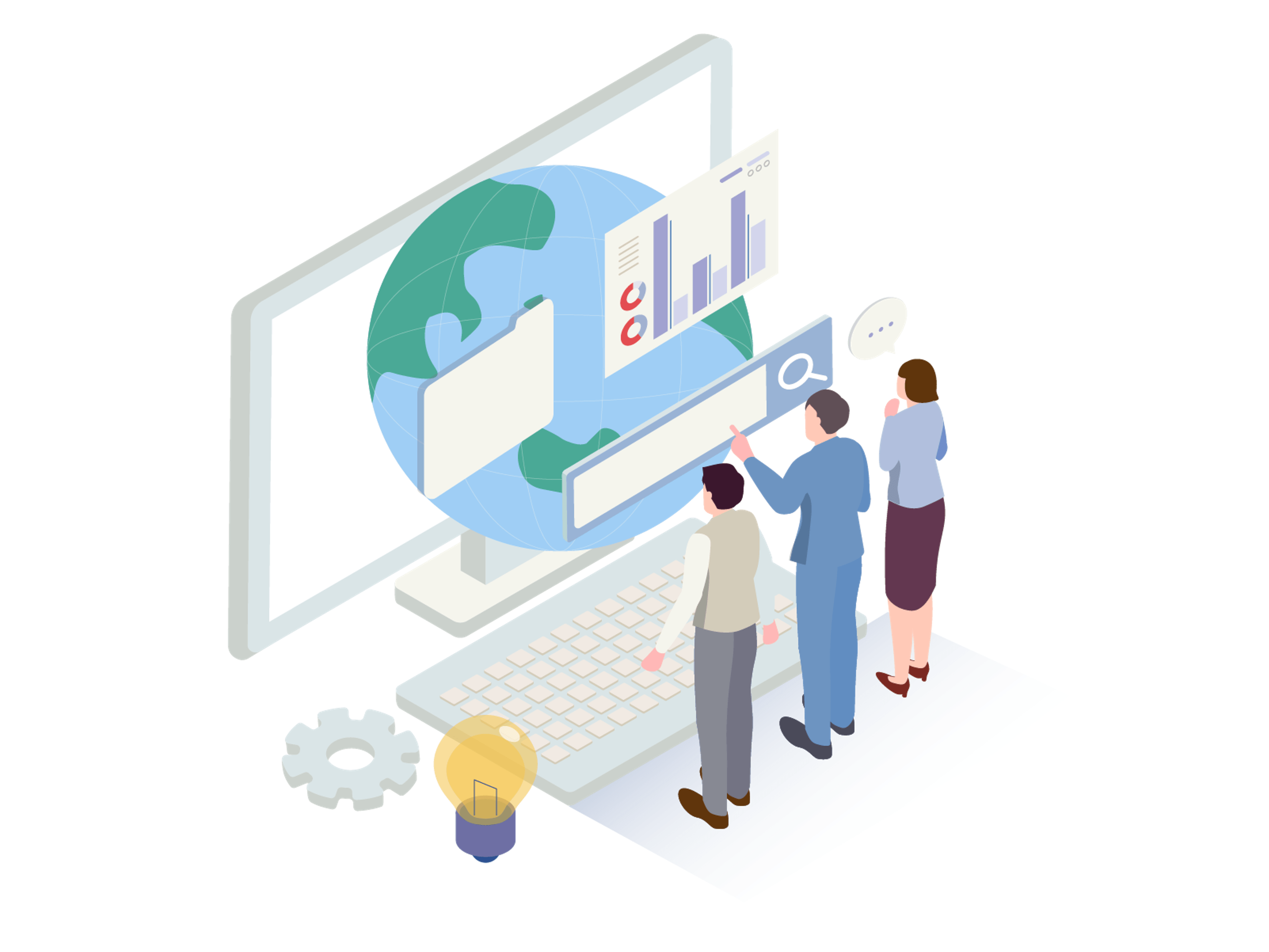
次に具体的な福利厚生の例をご紹介します。
以下のようなものが福利厚生費として計上可能です。
・通勤手当
・健康診断費用
・慶弔見舞金
・慰安旅行や研修旅行の費用
・忘年会や新年会等の費用
・従業員への食事補助
・残業時の食事代
・社宅家賃
・自社商品の値引き販売
・会社で契約する養老保険
ただし、それぞれに先ほどご紹介した4つの条件を満たしている必要があります。
・家族以外の従業員を雇用していること
・全従業員へ、平等な提供であること
・社会通念上妥当な金額や内容であること
・賃金ではなく、現金や換金性の高いものでないこと
例えば、通勤交通費であったとしても、1ヶ月あたりの通勤手当が15万円を超えると課税対象となります。
また、社宅家賃に関しても、従業員から賃料相当額の50%以上を徴収していない場合、家賃は課税対象となります。
それぞれについての社会通念上妥当な金額や内容については、税理士などの専門家に確認すると良いでしょう。
なお、昨今、導入を検討する方も多いカフェテリアプランですが、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランの場合、非課税(福利厚生費として経費計上)とすることはできませんので、このあたりについても注意が必要です。
個人事業主の福利厚生費に関するよくある質問と回答
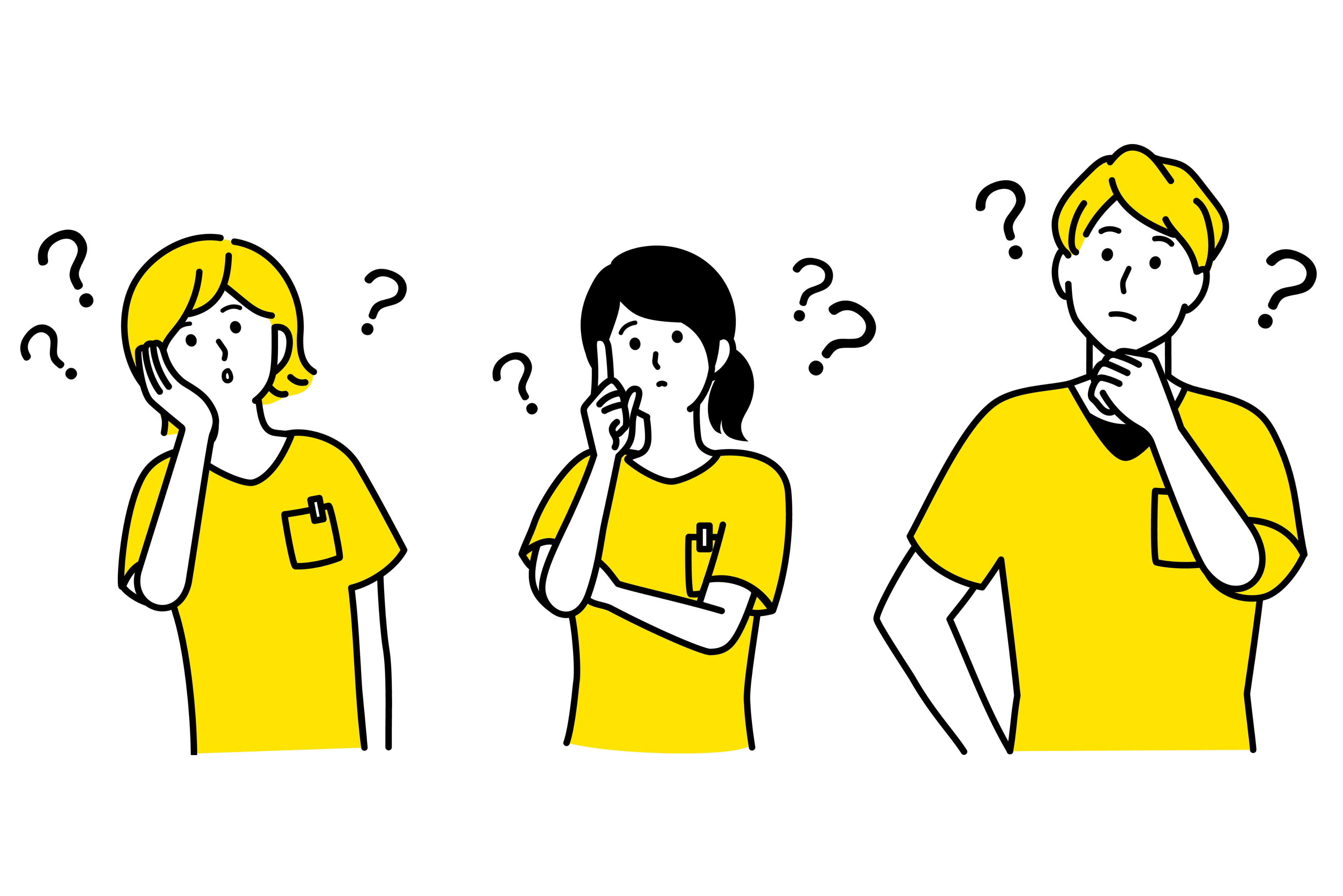
ここまでで解説してきた内容と一部重複しますが、福利厚生費の経費計上に関してよくある質問について、解説していきます。
個人事業主の福利厚生費に関する、よくある質問┃家族は使える?いくらまで使える?
とても多いのが、従業員としても勤務している家族についても福利厚生費を経費計上できるか?というご質問です。
まず、上述のとおり、個人事業主が、家族1人を従業員として雇用しているようなケースでは、福利厚生費の経費計上はできません。具体的には、青色申告者である個人事業主が青色事業専従者などの家族従業員と旅行にいった場合、これは家族旅行とみなされる可能性が高いです。
従って、いくらまで使えるかという点については、そもそも使えないという結論となります。
一方、家族以外の従業員もいる場合において、上述の4つの大枠の条件を満たす場合には、家族従業員の分も含めて福利厚生費を経費計上できる可能性があります。
個人事業主の福利厚生費に関する、よくある質問┃自分(事業主本人)1人でも使える?
福利厚生は「従業員のため」の支出である必要があります。従って、事業主本人の福利厚生費を経費計上することはできません。
個人事業主の福利厚生に関する、よくある質問┃福利厚生の上限金額はいくらまで?
福利厚生費として経費計上できる金額に明確な上限はありません。
ただし、例示などによって、おおよその金額上限が決まっているものもありますので、代表的なものをご紹介します。
■社員旅行:4泊5日以内、一人当たり10万円程度
ただし、以下のような細かな条件もあります。
※旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること
※不参加の従業員に現金支給などがないこと
参考:No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行┃国税庁ウェブサイト
■食事代:1人あたり月額3,500円(税抜)以下/1食あたり300円(税抜)まで
※条件は以下
通常の勤務時間に支給する食事
・従業員が食事代金の50%以上を負担していること
・企業側負担が、一人あたり月額3,500円(税抜)以下であること
深夜勤務の従業員に対し、現物での支給が難しい場合
・1食あたり300円(税抜)まで
参考:No.2594 食事を支給したとき┃国税庁ウェブサイト
■慶弔見舞金や健康診断費用
「社会通念上妥当な範囲」であれば上限はありませんが、高額すぎる場合、経費として認められない可能性があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?そもそも、福利厚生費の経費計上を、個人事業主の方でも活用できるという点は知られていません。
福利厚生を上手に活用することで、採用難や、人材の未定着といった、人の課題を解決しやすくすることができます。
ただし、要件があったり、それぞれに、金額的な上限があったりしますので、事前に調べたり、税理士等の専門家に相談してから導入すると良いでしょう。
この記事の監修者

峯クラウド会計事務所 代表税理士 峯 英之
キャッシュフローコーチ・融資コンサルタント
1981年4月24日生まれ
会計事務所と税理士法人で8年間の実務経験。税理士法人では、中小企業の税務サポート、上場会社の連結納税支援、信用金庫の相続税相談員などを担当。その後2015年7月から、個人事業主・1人社長に特化して新橋で従業員数15名の会計事務所を経営する。
特に法人税務に強く、代表的な例としては、税法に無いスキームを構築し実行し約21,000,000円の節税に成功したケースや、税務調査で約33,000,000円の納税額を減らしたケースなどがある。
最近では、個人事業主向けにマイクロ法人と個人事業主の二刀流を使った国民健康保険料・国民年金保険料の削減、1人社長に特化した節税と戦略構築、副業法人を活用した副業マンのサポート、に力を入れている。
Amazonで6冊出版。
https://lit.link/minemicrohoujin
この記事の執筆者

unite株式会社/株式会社Brand Communication/株式会社Ageless 代表取締役 角田 行紀
起業支援、事業支援や、最適な士業の無償紹介、士業が講師を務める企業研修事業(主に法務・労務・税務・財務)、経営者や士業などが講師を務めるセミナー事業などを行うunite株式会社と、ウェブマーケティング支援・ウェブ制作事業を実施する株式会社Brand Communication、建設業者とユーザーをマッチングする株式会社Agelessの3社の代表を務める。
多くの起業家からの相談や、士業による起業希望者へのアドバイス、自身の起業経験などを基に本稿を執筆。

